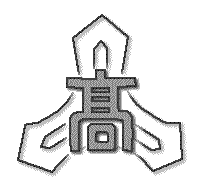厚木高等学校 応援文化の歩み
文責 田中文雄 (高20回)
応援団の歩みではなく応援文化の歩みとしたのは、中学時代より応援を指導する団体又は個人があり応援団的なものは存在していた。それから60年後に団は消滅している。その後にわか応援団となり常設の組織亡くなり継承しているので文化とした。
日本独自の文化として応援文化として扱うものとした。欧米ではチアリーダー、ブラスバンドがあるが、整然としてリーダーを立てての組織応援は無いといわれているので、日本文化として応援文化とテーマを設定したものである。また平成中期よりその70年後にかながわ校歌祭が始まり厚高応援文化は継承されていると判断する。
また応援思想の原点は大学応援、特に昭和30年代後半からは東京六大学応援を目標として形成されてきたことは歪められない事実である。特に六大学は他大学と違い応援リーダーのみの応援ではなく観客(大衆)とともに歩んできた経緯があるのでそこが厚高の応援思想となっている。これから述べる中で六大学云々の内容が多様に記述されるが、これらを基本としているからである。さらに応援団に関する周辺事情も加味しつつ述べていきたいと思います。
黎明期
応援の起源として1931年(昭和6年)頃から非公式の自主応援団(又は個人)が第三中学時代より存在していたものと推定されます。団史記録によると、このころから全校生徒を集め応援練習、風紀指導をしていたとあります。中学時代はバンカラ風応援で第二応援歌が作成される前は「こちゃえ節」などが唄われいたようです。むろん第一応援歌、出来立ての校歌も存在していたものと思われます。現代から見ればスピード、リズム感はほど遠いものとだったと思われます。
ここで同じ高校(当時中学)の黎明期を探ってみます。埼玉六校応援団を例にとって見ます。大正末期に春日部高校に応援団が創設されています。その他、松山、熊谷、浦和高校等は昭和初期に作られたようです。さらにさかのぼり明治29年に水戸第一高校と宇都宮高校の野球試合で応援がなされたとの記録もあるようです。どの段階で創設されたか公式か非公式化は定かでないが我が厚高応援団もおそらく昭和初期と思われます。
少なくとも第二応援歌が昭和8年、校歌が昭和6年であり、第一応援歌は制作年不詳ですが、その間の第一応援歌はは制作されたと見て間違いないと思われます。校歌及び第一応援歌が制作されたとして、それをリードする団体(個人)いわゆる応援団がいなければ唄われないと思われます。よって我が厚高は昭和6年~8年の間に非公式ではあるが応援の文化を開始されたと思われます。
また1915年(大正4)に全国中学校優勝野球大会が開催される様になり、1923年(大正12年)に真岡中学(栃木県)と下妻中学(茨城県)の大会では応援団同士の乱闘騒ぎで翌年の関東大会が中止された記録もあります。時代を超えて応援団問題は常にあったようです。
話は少し脱線しますが、応援文化を語っているのでその裏社会・裏文化としての「厚高隠れ歌」の一部を紹介します。制作年・作者はいずれも不明であるが、おそらく黎明期か創設期に作られ他と思われます。「数え歌」~一つとせー人は見かけによらぬ者・・、「ツンツン節」~ボクは厚高の三年生 胸に五つの金ボタン・・、「チンカラ小唄」~チンカラ カンコラ 学校サボって下界にいけば・・、「能天気節」~在か厚木か 厚木か在か 空にゃ厚女の 鐘が鳴る・・ 以上4曲があります。応援団をはじめとし運動部などで、当時、帰宅時の駅までの田んぼあぜ道で歌われいたと思われます。
創設期
黎明期初期から20年後の1953年(昭和28年)に厚高応援団は正式に設立されました。三剣精神・三徳精神の下、質実剛健の気概、奉仕の精神による設立でした。構内組織としては、生徒会と同等に新聞部と並んで位置ずけられました。中学時代から、当時は文武両道の精神により部活動が活発で各運動部各文化部での応援に要請されました。昭和20年代には新制高校となっており、大学野球の応援方法が採用されました、特に応援団卒業者が大学応援団に入部した事もあり積極的に模範とするようになりました。特に東都大学野球応援手法が取り入れられましたがスピード、リズム感は確立されていませんでした。また、学校当局及び一般生徒との軋轢もあった様で活動には種々問題があったようです。
ここで東都大学応援方法と、のちに採用される東京六大学応援方法の差異を解説します。現代では両者ともリーダー、チア、ブラスバンドの三部門の応援となっていますが決定的に異なる所は、観客(大衆)主体の応援であるか否かの違いであります。野球そのものの「実力東都」と野球そのものとスタンドの応援を含めた「人気の六大学」の違いがあります。歴史を考察すると東都今から80数年前(現プロ野球も同じ)、六大学は90数年前の開始となっている。特に六大学の起源はその20年前の今から110数年前(明治末期)の早慶戦からのスタートとなっている。
当時(明治末期~大正~昭和初期)は現代のようにプロ野球、Jリーグ等さほどスポーツ娯楽の無い時代であり学生はもとより一般客は学生スポーツに熱が入っていた時代である。観客が多いということは、何ら客席に統制が取れていなければ試合に熱中すれば最悪、暴動があったようである。現代で言う場内整理員とかが居ない時代であろう。特に早慶戦では「リンゴ事件」があり昭和初期に20年間近く試合が実施できなかったという記録がある。そこで、いわゆる応援団リーダーが自然発生的に生まれ客席を統制し整然と応援する形となったと記録されている。
今応援で行われている試合前後の校歌斉唱・エール交換・代表応援歌交換等は、整然とさせる為のイベントである。特に早慶戦では試合前の校旗(団旗)入場、試合後の学生歌斉唱、勝利の拍手等のイベントが行われている。試合前後はもとより試合中の応援曲、マーチ等のチャンス時の応援も必然的に要求に答えるものとして成長して来たものと思われる。よって応援団リーダー組織は観客主体の組織応援となっていくことになる。一方「実力東都」は平日開催(六大学は土日)の為、観客がさほど集まらず、観客主体の応援方法からは遠ざかっていたのが現状である。
発展期
1962年(昭和37年)に応援団の在り方の種々問題を払拭するために、公選制応援団がスタートしました。同時に矢継早に組織応援の形を整えていきました。全頁で解説した東京六大学野球応援方法を全面的に取り入れ、新規応援歌の作成、中間リーダー方式の採用、各種機材(団旗、椀章、リーダー台、バッチ等)、ブラスバンドとの連携、応援団指導部(幹部)の整備、昼休み全体練習、幹部合宿等があります。また活動は野球応援、駅伝応援、北相陸上応援、壮行会、風紀取締、団報の発行、応援歌集の発行等があります。指導部組織として団長、副団長、総務部長、リーダー部長、会計部長、旗手部長、編集部長、という役職を設定し責任を持たせました。また学校側で顧問の先生を選出し、監査役としていました。一般生徒は全員応援団員と定めました。
新規応援歌等については同窓会HP「応援歌80余年史」を参照されたい。中間リーダー方式について説明します。観客全体を指揮するリーダー台上のリーダーはプレイそのものを確認できる事はできないので、まず指令者をリーダーの前に置きプレイ状況に応じてリーダーに指令を出す。
次にスタンド最上段に位置しているいわゆる「鏡」がリーダーを真似てスタンドに配置された複数中間リーダーに指示し、中間リーダーは近場にて観客を直接応援指導する形となる。いわゆるこれが組織応援となりうる事となります。よって中間リーダーが応援の主役実働となります。
団旗については木綿生地であったものを絹生地(軽い)ものとし、大きさも大団旗とした。腕章については新規デザインとし、臙脂色ベースで三剣マークと厚木高校のロゴ及びストライプ入りとし材質は高価なフエルトタイプとし丈夫なものとした。昼休みの一般生徒(団員)の全体練習については、旧制第三中学校時代から30数年あまり継続で実施しているので、当然のごとく行われました。また応援団の活動方針等を一般生徒に周知させる為の宣伝活動として団報の発行を不定期ですが実施し、また応援歌を周知させるために生徒手帳に歌詞の記載、応援歌集の発行、及び応援団史の小冊子の発行(現在まで2回作成)も実施されました。
応援活動そのものについては、高校野球で数回スタンドでの人文字の実施、中でも昭和40年代には人文字用カラーパネル(表裏2色)で色彩鮮やかな応援を繰り広げました。また先ほどの宣伝活動の一環として各種試合完了後に新聞部写真班と連携し校内掲示板に試合状況・応援状況の写真張り出し報告も行いました。また得点時の歌「ああ愉快だね」でスクラム組での歌唱時に盛り上げの為小旗を数本作製しました。その後厚高賛歌としてうたわれる「健児は建てり」の時も使われるようになりました。応援リーダーの服装も学ランだけでなくセーター(臙脂色ストライプにAのロゴ入り)も採用されるようになりました。以上のような応援手法によりこの時期には高校野球連盟の「応援団賞」を数回受賞しています。
充実期
昭和50年中期にはさらに8番目の新応援歌(創立80周年記念)及び新応援曲が2曲作られ公選制応援団の充実期を迎えました。応援曲あるいはマーチに関してはそれまでは「いざや往かん」であったが楽曲とコールを組み合わせた曲がなく、チャンス時に長時間にわたって吹奏楽主体の楽曲がありませんでした。そこで「栄光のマーチ」、「勝利のマーチ」が学内吹奏楽部有志の手で作成されました。さらに六大学である法政大学の「チャンス法政」と同楽譜の「チャンス厚木」も制作されたが、厚高オリジナルではなかった。過去において応援曲・マーチは「いざや・・」、「ラランカラン」、「ジェンカ」、「栄光の・・」、「勝利の・・」を含め6曲となり充実していくこととなる。
新応援歌は第二の「燃ゆる闘志」として簡潔・明瞭に当時の学生生徒に親しまれ歌われる様になりました。これで厚高歌は応援歌8曲、応援曲(含マーチ)6曲となり名門大学応援団と肩を並べる事となりました。
応援曲に話を戻します。校歌・応援歌は各校のオリジナル性が基本となっているが、応援曲の方は特にオリジナル性を求められているものでは無いと思われる。確かに早稲田大学吹奏楽部の「コンバットマーチ」は製作者の意図は誰でも演奏してもらえるように作ったと発言している。名門大学の吹奏楽部は楽譜を公開しないとは発言していない。現に同上「コンバット・・」は高校野球甲子園でも各校が演奏しているのが見受けられる。また六大学でも応援曲として明治「狙い撃ち」、法政「アルプス一万尺」、立教「ポパイ」、東大「アトム」などだれでもが知っている曲であり観客が乗りやすい事を考慮し演奏されている。厚高では厚高賛歌「戸室ヶ丘」、「ラランカラン」、「ジェンカ」の3曲がオリジナルではない。以上まで応援団自体の内容に関しては「厚木高等学校応援団史」を参照されたい。
継承期-野球応援
時代は昭和から平成に変わった平成4年に公選制応援団は廃止されました。時代はみんなで往こうという全体主義的考えでなく、個人主義的な考えに世の中が変わりつつある時期でした。よって応援団も前近代的な考えとなり大衆に指示される事は無くなっていったものと思われます。昭和初期からの長い年月のなかで、応援団の存在は常に紆余曲折がありました。
しかしながら各種スポーツ応援、特に野球大会は多くの関係者が集まるので、応援をリードする人が必要と考えられていたと思われます。野球部のベンチ入りできないメンバーにより、にわか応援団が組織され前頁に記述されたある程度の応援方法を継承していくようになりました。
常設の組織がなくともある程度(1か月程度)あれば応援リーダーは可能と思われます。現に都市対抗野球応援でもその程度の時間で立派に各企業(都市代表)がスタンドを賑わしています。それも学校で言えば過去の諸先輩が作った応援歌やりーディングがあるので、可能になっているのです。企業で言えば学生時代に応援団を活動していた社員がいるから可能であると思います。
ここで現状の応援方法と公選制時代の方法とを比べてみます。試合前の校歌・エール交換は行われていなく第2回イニング開始じに行われている。これは第2試合以降スタンド観衆の入れ替えで時間的余裕が無いためである。試合後は実施されている。校旗(団旗)は試合中にスタンド最上部で常時掲揚されている。公選制時は試合前後の校歌・エール交換時のみ掲揚されていた。全9回の各イニングの開始時の応援歌は歌唱されていない。攻撃チャンス時に応援歌・応援曲・マーチが演奏・歌唱されている。エール(勝つぞ厚木)・ソーラ厚木等は部分的に実施されている。演奏は吹奏楽部OBの有志及び軽音楽部のピアニカ等で実施されている。吹奏楽部としての活動ではないようである。チアのダンドリ部は顧問の先生の指導により華やかに演舞されている。用具としては野球部父兄会の用意する黄色メガホン・応援歌歌詞・野球部メンバーリストが配られている。スタンドを盛り上げるためのリーダーによる「学生注目」及び守備時のコール(チャチャチャ厚木等)も実施されていない。しかしながら試合終了後、勝っても負けても野球部員と応援団・バンド・チア・父兄・教職員・生徒(自由参加)・OB等が集合し健闘を讃える挨拶の交換を行っていることは見ていて気持ちいいことである。
公選制時代の応援方法は現在作成検討中の「野球応援方法マニュアル」を今後参照されたい。以上基本的には微弱ではあるが過去の応援方法は継承しているものと思える。新しい形のものが生まれてくれば、伝統と進化を融合するものとなっていくと期待するところである。
継承期-かながわ校歌祭
2006年(平成18年)に神奈川県の声掛けにより校歌祭がスタートしました。厚高応援団廃止になって14年後のことです。神奈川県内の公立高校の卒業生・現役生を主体に「校歌・応援歌等の伝承と振興」を目的としたものです。主幹は各校同窓会(厚高は戸陵会)となり、企画は戸陵会と応援団OB会が実施しています。また吹奏楽部OB有志(高20回代卒)、ダンスドリル部OB及び現役が主導し一般OB約100人余り、現役生20人余りとともに一体となって厚高歌を高らかに唄っています。なおダンドリ部は2005年に全米ダンスドリル選手権で優勝し、数年前には準優勝しています。また元アメリカNFLチアリーダー堀池薫子を輩出しています。吹奏楽部については1960年代に一世を風靡したクレージーキャッツの安田伸(故人高3回卒)が創部した歴史ある部であります。これらも過去において、諸先輩が熱い情熱で築き上げられたものと思います。
毎年4月以降に同窓会事務局・応援団OB会執行部・吹奏楽部OB有志代表・ダンドリ部顧問の4者による企画会議・応援団OB会進行練習・3者練習・一般OB全体練習を経て本番に臨んでいます。また本番後は厚木市内ホテルにて、同窓会主催懇親会を実施しています。懇親会では、厚高のほとんどすべての応援歌、応援曲、マーチ、音頭等が余興で吹奏楽の演奏の下披露されています。また応援団OB会では反省会が年末に実施されています。本番では校歌はむろん、「栄えあれ・・」 「健児は・・」 「栄光の・・」 「勝利の・・」 「いざや・・」 「精鋭の・・」 「第二・・」等が過去に唄われました。
厚高は他校に先導し毎回絶賛される演技をしています。演技スタイルも当初はバック音源のみで歌唱、その後吹奏楽部OB有志の参加希望で共演となり、現行はダンスドリル部OGが顧問の先生の指導の下に三位一体で共演しています。